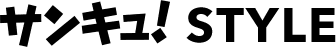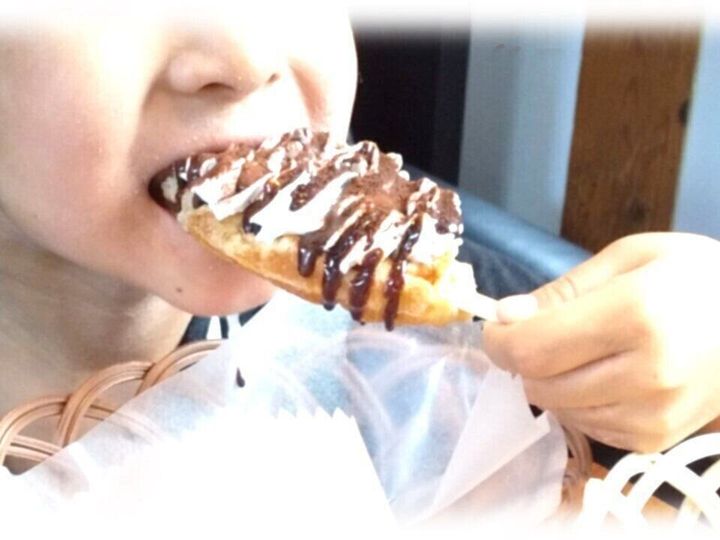
太りやすい原因は「味覚」が鈍っているから⁉管理栄養士がおすすめする味覚改善のポイントとは?
こんにちは。太りにくくおいしい食べる方法を探求している、サンキュ!STYLEライターのゆかりです。
「ダイエットしなくちゃ」と思いつつ、スナック菓子や油っこいものがやめられないという人、周りにいませんか?
じつはこれって、味覚が鈍っているせいかもしれないのです。
この記事では、管理栄養士である筆者が、味覚と肥満の関係についてわかりやすくご紹介します。
また、鈍った味覚をもとに戻すための方法についても触れているので、参考にしてみてくださいね。
味覚には「第6の味」がある?
味覚というと、5つの味があることをご存じの人も多いのではないでしょうか。
甘味、塩味、うま味、酸味、苦味の5つが基本的な味として、口の中に入れた飲食物に含まれる成分から、脳が味を判別しているのです。口の中(おもに舌)には味を感じ取る細胞があり、そこに特定の成分が触れることでそれぞれ異なる神経を通じて脳に刺激が送られ、わたしたちは味として認識することができます。
ところが、近年の九州大学の研究により、脂肪が含まれていることを脳に伝える新たな神経が見つかりました。そのため、「脂肪味」が6つめの味として注目されるようになってきたのです。
「第6の味」と肥満の関係とは?
関西医療大学の研究によると、肥満の人とそうでない人で味覚を比較した結果、脂肪味は肥満の人のほうが鈍いことが報告されています。
なお、摂取カロリーと脂肪味の鈍感さが関連しており、太っていても運動不足のせいで摂取カロリーがそれほど多くない人の場合、あまり脂肪味の鈍さは見られなかったと言われています。
一方で、肥満の人を入院中に減量させることで、減量前と比較して脂肪味が敏感になっていたことがわかったのです。
これらのことから、つぎのようなことが推測されるのではないでしょうか。
・肥満で摂取カロリーが多い人は脂肪味に鈍感になる。(その結果、脂肪が含まれたものを多くとりやすくなる)
・肥満であっても減量することで脂肪味の感度が改善する。(その結果、脂肪味に敏感になり、脂肪が含まれたものを少しとっただけで満足しやすくなる)
味覚を鈍らせないポイント
脂肪(脂質)には、体温を保持したり、細胞膜やホルモンの材料となったりするなど、私たちの健康を守るために欠かせない役割があります。
しかし、1gあたりに9kcalと多くのエネルギーを含むため、必要以上のとり過ぎは体脂肪として蓄えられたり、血液中に多く含まれて生活習慣病などを引き起こすことに……。
普段から脂肪を多くとっている人ほど、その刺激に慣れて脂肪味に鈍くなるのだとか。そのため、脂肪味が鈍い人ほど、脂肪をたっぷりととらないと満足感が得られなくなってしまうのです。
そこで、脂肪をとりすぎないための食事の内容の改善ポイントとして、つぎの5つを意識してみましょう。
1. 揚げ物や炒め物は、蒸し物や煮物に。
2. 脂身の多い肉や魚は、脂身と皮をはずしたり、脂身の少ない部位を選ぶ。
3. こってりとしたスープのラーメンよりも、そばやうどんを選ぶ。
4. バター、クリーム、チーズなどが使われた洋菓子やアイスクリームよりも、あっさりとした和菓子、シンプルなせんべい、シャーベットを選ぶ。
5. マヨネーズは、半量をヨーグルトと塩こしょうで置き換えて使うか、ノンオイルドレッシングに置き換えを。
実践のポイントを押さえて、ぜひチャレンジを!

最初は物足りなさを感じる人が多いですが、10日続けると徐々に慣れていきますよ。その理由は、味を感じる舌の細胞は、10日ほどで新しく入れ替わるからです。
こういった食生活を実践できれば、無理なくカロリーのとり過ぎも減らせるので、味覚改善とともに減量効果も期待できるはず。
ご紹介した内容を参考に、普段の食事を見直して味覚の衰えを防いでみてくださいね!
参考サイト
★この記事を書いたのは・・・管理栄養士&食生活アドバイザーのゆかり
小学生女児のママ。食べること・料理をすること・喋ることが好き。講師、食材記事の執筆・監修、食育サイトの栄養相談や献立作成などで活躍中。個人で食育イベントの実施や、YouTubeチャンネルを運営しています。