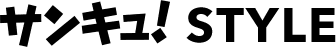卒業してもランドセルとっておいて!捨てずに活用させる手放しかた
こんにちは。サンキュ!STYLEライターのdanngoです。
小学校を卒業するととたんに使わなくなるランドセル。愛着もあり捨てるのがもったいなくも感じられますね。
場所をとるので結局捨てる人が多いと思いますが、できればしばらく手元に置いておいてほしいのです。
有効活用できる手放しかたを紹介します。
ランドセルは寄付できる

ランドセルはそのまま捨ててしまうか、小物にリメイクして使うかの2択だと思っている人が多いようですね。
じつは第3の選択肢、「寄付する」というのが残っています。
「みんな新しいのがほしいのだから、寄付なんて無意味なのでは?」と考えるかもしれませんね。でも、必要としている人がいるのです。
今は日本のランドセルが発展途上国で人気なのだとか。丈夫で長持ちするランドセルは実用性が高く、デザインも豊富なのだから納得です。
寄付は、NPO法人などを通じておこなうことができます。検索すると複数の団体が見つかるので比べてみるといいでしょう。
私は送り先が比較的近場であることを考慮し「もったいないジャパン」というところを選びました。ランドセルだけではなく、日用品・食料品などを幅広く受けつけています。
箱につめて送るだけ

寄付するとなるとなんとなく手続きが面倒そうに感じられるかもしれませんが、実際はそんなことありません。
寄付先によっても違いはありますが、「もったいないジャパン」の場合は梱包して指定の住所に送るだけでした。特に予約は必要ありません。
かかった費用は、送料の1,750円だけ。普通ごみとして捨てるのよりは高くつきますが、万単位のリメイク費用に比べると安いです。
むだが出ずそのまま有効活用されるので、地球に優しいですよね。
ひとまず捨てるのは待ってみて

じゃまだしお金もかけたくないから、卒業したらすぐに捨ててしまいたいという気持ちもよくわかります。それでも多少迷う気持ちがあるなら、ひとまず捨てるのは待っておきましょう。
というのも、いきなり捨てられると子どもがショックを受けるかもしれないからです。
私は小学生のときに使っていた赤いランドセルを卒業してまもなく捨てられてしまいました。事前に捨てると言われていなかったので、ある日急に部屋から消えたという状況です。
そこまで思い入れがあったわけでもないのですが、愛猫が子猫の頃よくランドセルに隠れていたので、空にしておけばまた入るのではという期待がありました。いきなりなくなったのは少し残念でした。

持っていても意味がないとしても、子どもにとっては6年間のがんばりがつまったランドセルです。子どもと相談して、目立つ場所に飾ったり背負わせて写真を撮ってみたりして、気がすむまで思い出を楽しんでほしいなと思うのです。
◆記事を書いたのは・・・danngo
物心ついた時から生き物大好きだった40代主婦。美しく平和な地球と子どもの未来を守りたいと考えています。面倒くさがりのため、できるだけ手抜きしてズボラでもできるエコ活動を模索中。