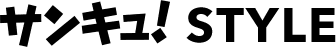子どもがいても片づけしやすくする工夫について
子どもが乳幼児の頃にいつも家の中が散らかってモヤモヤしていたサンキュ!STYLEライター、整理収納アドバイザーのきいろです。
子どもが乳幼児の時って、見えるもの全てが子どもにとっての興味対象で、子どもは何でも触って確かめますよね。その姿はかわいくて、面白いですよね。
でもいろんなものが引っ張り出されては遊ばれて散らかっていて、それを片づけて大変だったなと思っています。
乳幼児の頃は散らかっていてもしょうがない

筆者は妊娠中に整理収納アドバイザーの資格を取って片づけに興味があり、片づいた部屋が好きでした。
でも子どもの好奇心の強さは何物にも変え難いでしょう。
保育園に子どもを入れるまではずっと子どもと一緒にいて、子どもにご飯をあげて、歯磨きをし、遊びに付き合い、昼寝をさせて、時には昼寝をしないこともあり、子どもの機嫌を気にかけ、料理をして、お風呂に入れ、子どもの健康に気遣い…とこれを毎日しているだけで精一杯で疲れていた気がします。
片づけは二の次、もしくはそれよりも後にするしかなかったと思います。
でも「散らかっていても死ぬわけじゃないし」には心から頷けなかった

睡眠とか子どもやお母さんの笑顔や健康の方が大事。それは当たり前のことでわかっています。
でもよく目にした「散らかっていても死ぬわけじゃないし」という慰めの言葉はわたしにはあまり効きませんでした。
死ぬわけじゃなくても、毎日目にする景色が心地よいか、そうでないかはわたしにとっては重要でした。
1日に1回でもきれいな状態にすると気持ちよくて、精神的に落ち着くことができたと思っています。
散らかるのは当たり前だけど元に戻しやすい部屋にする
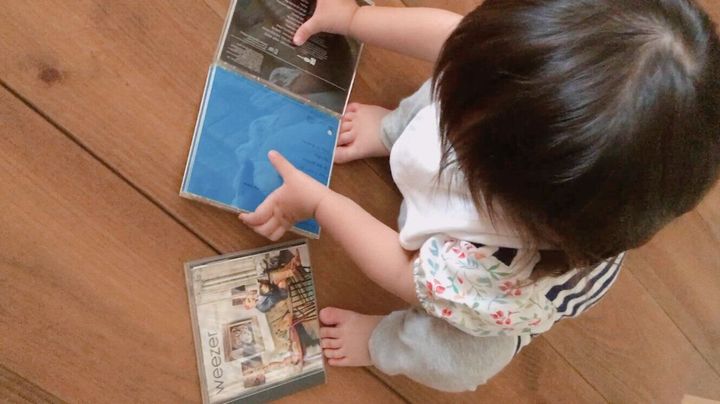
子どもが遊んで散らかるのは当たり前なので、散らからない部屋にするのは無理だなと思います。
でもせめて物を元に戻しやすい部屋に工夫をすることは大切だなと思います。
たくさんの量を元の場所に戻すよりも、少しの物を戻しやすい場所に戻せた方が労力が少なく済んで楽ですね。
よく遊ぶおもちゃとそうでないおもちゃを別の場所に分類

はじめはおもちゃは全て同じところに収納していたのですが、こうするといろんなおもちゃを次から次に出して片づけが大変だったため、途中からよく遊ぶおもちゃや見てほしいおもちゃのみ目に入りやすいところに置いていました。
反対にそうでないおもちゃや遊ぶ頻度が低いおもちゃは少し遠くに収納し、目に入らない場所に置いていました。
そして時々おもちゃを入れ替えたりしていました。
関心が低くなってきているなというおもちゃは暫く距離を置いてから手放したりすることもありました。
このように分類して、一度に出すおもちゃを少なくするおかげで、おもちゃを元の場所に戻すことが楽になりました。
もう小学2年生ですが、このよく遊ぶおもちゃとそうでないおもちゃを分類して別の場所に収納するというのは続けています。
大人も子どももたくさん物が出ていると片づける気がなくなる

「片づけなくてもまた使うし、出しておけばいいじゃん」という人もいるのですが、出しておくと、その景色に見慣れてしまいます。
出しているのが当たり前になって、出したままになると、また別の物を出してそれが集まっていきます。
たくさんの物が出ていると子どもでも大人でも面倒になって片づける気がなくなります。なので遊んだら片づけるという「区切り」は大切だと思います。
でも工作などで途中まで作った物をそのままにしておきたい気持ちはわかります。その続きからやりたいですよね。
そしたらそれを邪魔にならない場所に置いて、その他の物は片づけます。
「散らかったのをそのままにしない」、そしてモヤモヤした時は人に頼って、片づける時間を作るのがおすすめです。
◆この記事を書いたのは…きいろ
整理収納アドバイザー、クリンネスト。
シンプル・サステナブル・整えるをテーマに暮らしの気づきや片づけのこと、サステナブルなアクションなどを投稿しています。