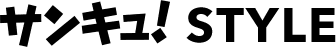お米を健康的に節約する春の薬膳の知恵
- 知って活用、暮らしに溶け込む健康づくりをモットーに東洋医学のセルフケアの知恵を取り入れやすく続けやすいように発信します。看護師・薬膳師・などの資格をもつ令和元年生まれの坊やのママです もっと見る>>
看護師で薬膳師の薬膳ナースけいこです。
お米の価格高騰で「お米を食べたいけれど頻度を減らしている」「子どもが食べ盛りでお米がすぐなくなるから家計が圧迫されている」といったことはありませんか?
今回は、春の薬膳の知恵を使って健康的にお米を節約する方法をお伝えします。
デトックスしながらお米の節約
寒い冬には、人間は水分や脂肪、老廃物などを体内に溜めこむという性質があります。この老廃物などをデトックスしてくれる力があるのが、春の山菜です。
春の山菜といえば、ウド、タラの芽、フキノトウ、ワラビ、セリ、ツクシなどが代表的です。程よい苦みがクセになり、ご飯と一緒に炊き込むことで、ちょっとしたかさ増しにもなります。
春の芽吹きに備えて力を蓄えていた山菜の食材パワーを借りるだけでなく、鮮やかな緑が食卓に並ぶと、穏やかな気持ちになりますよね。
春の定番食材でお米を節約
春の定番といえば「たけのこ」です。炊き込みご飯の具材としてもおなじみで、たけのこご飯を毎年楽しんでおられる家庭もあると思います。タケノコがたっぷり入ったごはんはホクホクして味わい深く、ボリュームも満点ですよね。
薬膳では、タケノコは
・体内の余分な熱を冷ます
・痰や咳を和らげる
・むくみを和らげる
・便秘を改善する
力があると考えます。
あく抜きなどで、手間がかかる印象がありますが、下処理を終えたタケノコが市販されていることもあるので、活用してみると時短になりますよ。
消化を助ける節約
春は、お花見や会合、外食など普段とは異なる時間に食事を摂ったり、揚げ物など消化の負担になるものを食べたりして胃腸が疲れやすいタイミングでもあります。
「お粥」として調理すれば、多くの水分を含むためお米の節約になるだけでなく、消化に良い形態となるため胃腸のケアにも繋がります。
さらに、お米自体に、体にエネルギーを与えたり、胃腸の働きを助ける力があります。
また、お粥のトッピングとして、鮭フレーク、海苔の佃煮、梅干しなど様々なバリエーションを楽しむこともできますよね。
お米の価格高騰は家計の負担になりますが、春の食材を楽しみながらお米の節約をすることで、より健康になりましょう。
◆この記事を書いたのは…薬膳ナースけいこ
看護師・薬膳師・経絡ヨガ指導者・薬膳茶エバンジェリストなど人の心身のケアに関わって25年
東洋医学、西洋医学、脳と心の仕組みを使って「大人女子の体と心の生命力がUPする」健康習慣をお伝えしています
プライベートでは、令和元年生まれの男の子の子育てに奮闘中です