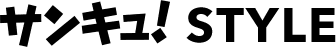「動画見せすぎ?」と思ったら!子どもの好奇心を育てる3つの工夫
暮らしのモヤっとする時間を短縮!サンキュ!STYLEライターで時短研究家ママのあらきあゆみです。
家事や仕事をしている間、子どもが動画を楽しんでくれていると、助かるなと感じることもある反面、「このままでいいのかな?大丈夫かな?」と、視聴時間や内容にモヤっとすることもありますよね。
しかし、動画を見ること自体が悪いわけではなくて、大事なのはどう向き合うか。私は、子どもの「動画タイム」を、好奇心を育てるチャンスとして捉えています。今回は、そんなわが家で実践している、動画タイムを「納得して使える時間」に変えるための3つの工夫をご紹介します。
動画を「遊び」につなげてみる
子どもが夢中になる動画の中には、カラフルなお菓子やスライムなど、大人目線では「うーん」と思うものもありますよね。
わが家の場合、それをすぐに否定するのではなく「きれいだね!これ作ってみようか」と次の遊びに発展させるよう子どもに提案しています。ただ見るだけで終わらせず、粘土や折り紙で再現してみたり、色づかいを真似してお絵描きしたり。
最初はやりたがらないこともありますが、私が横でやり始めてしまえば気になってやり始めてくれることが多いです。動画のサムネイル通りの写真をとってみて、見比べながらそっくり出来れば満足感もあって◎受け身の動画タイムが、主体的な「遊びの時間」に変わりますよ。
動画を「興味のヒント」にしてみる
わが家では基本的に子どもが自分で見たい動画を選びます。心配になることもありますが、子どもがどんな動画を選んで今どんなことに興味を持っているのか、どんな傾向があるのか知るための大きな手がかりになるからです。
履歴を一緒に見ながら「最近これよく見てるね!どんなところが好き?」と声をかけてみると、親が思いもしなかったポイントを楽しいと感じていたり、そこから新しい遊びやお出かけのヒントが得られたりします。
たとえば音楽系が多ければ、その音楽を家でのBGMとしてスマートスピーカーで流したり、カラオケやコンサートごっこに誘ってみたり。動画を通じて子どもの興味に合わせた会話が増えるのも嬉しいポイントです。
フィクションとして楽しめる力を育てる
動画の中には、親目線では「ちょっと刺激が強すぎる」「教育上、良くない」と感じるものもありますよね。しかし、子ども自身も意外と「これはお話の世界」と分けて見ていることもあります。
例えば、絵本では動物がしゃべっていても、それを現実とは混同していないように、動画も「フィクション」として楽しんでいるケースも。
もちろん、真似してほしくない言葉や行動があれば、きちんと声をかけたり、必要に応じて視聴設定を見直すのも大事。わが家でも最終的に視聴禁止になった動画はあります。
ただ、「これは現実とは違うよね」とか「お母さんはこれは好きじゃないな」と一緒に話せる関係があれば、それも大切な学びの時間になります。子どもがフィクションを楽しんでいるのに、大人が「ノンフィクション化」してしまうことを避ける、というのがわが家の動画との向き合い方の1つです。
最後に
動画もゲームも、ただ「見せすぎはよくない」「悪いものには触れさせない」と決めるのではなく、どんな時間として使うか、どんなふうに付き合うかが大切なんだと感じています。
たとえ必要に迫られて動画を見せているとしても、そこには「少しでも子どもに楽しい時間を過ごしてほしい」という親のやさしい気持ちがあるはず。だからこそ、モヤっとしたままで終わるのは、もったいないなと思うのです。
無理なく、罪悪感なく、自分のスタイルで心地よく。動画タイムも、親子の時間として前向きに活用していきましょうね!
◆この記事を書いたのは・・・サンキュ!STYLEライター&時短研究家ママ(あらきあゆみ)
プチプラ活用・デジタル活用・マルチタスク術など……ママのモヤっとする時間を短縮する問題解決のアイデアを提案|育児と介護のダブルケア◎年長&年中のやんちゃ男子の母、80代義母と同居中|FP2級&終活ライフコーディネーター。